吉備大臣
吉備大臣 中新里
中新里では、昭和の初めの頃まで、きびを作ることが禁じられていたそうです。その理由は、次のような伝えがあったからです。
字の鎮守様「御霊神社」は、天津児屋根命(あめのこやねのみこと)を祀っていますが、一緒に「吉備大臣(きびだいじん)」を祀っています。
昔、この吉備大臣が戦に出かけ、戦場で、乗っていた馬がきびに足をとられてよろめいた際、不覚にも落馬して負傷してしまいました。このため、吉備大臣を祀る中新里では、きびを作ることを嫌ったのだということです。
もっとも、吉備大臣とは奈良時代の学者で廷臣だった吉備真備(きびのまきび)のことですから、事実とは思われません。昔の人が、吉備ときびの音が似ているので、こんな昔話を作ったのでしょう。
栃木県のある地方でも、神様がきびの葉で目を痛めその氏子はきびを作らない(日本の伝説)など、似た話は日本中にあります。
近くでは、妻沼の聖天様の松嫌いの話があります。昔、聖天様と、太田の呑竜様が戦さをし、太田の金山まで攻め込んだ聖天様が、松の葉で目をつき、難渋して以来、妻沼地方では松を植えなくなったという話が伝えられています。
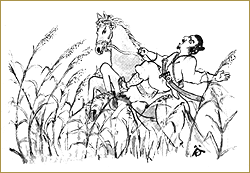
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
生涯学習課 文化財担当
〒367-0311
埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原1088
電話番号:0274-52-2586
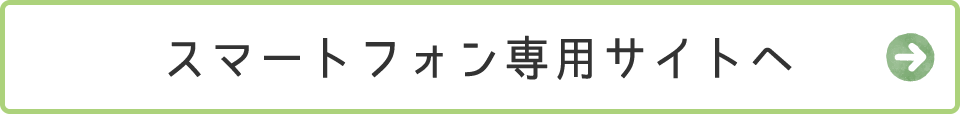


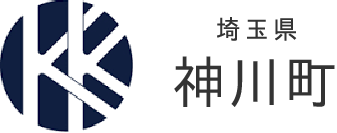
更新日:2018年06月27日