米に関する害虫イネカメムシについて
イネカメムシとは
近年、県内では斑点米カメムシ類のうちイネカメムシの発生が拡大傾向にあります。
イネカメムシは、斑点米及び不稔米を発生させる恐れがあり、発生量が多いと大幅な減収となる可能性があります。 イネカメムシの特徴として、体長は約13ミリメートル、黄褐色で背部両面に白色帯を持つやや細長いカメムシです。
7月頃から水田に飛来し、穂を加害するため、ほ場での発生状況を確認し、適期防除を実施しましょう。
詳しくは、埼玉県ホームページをご参照ください。
除草時期について
暖冬等の理由で越冬したイネカメムシは、落ち葉や雑草地から米の若い穂を求めて水田に移動します。
出穂前3週間と出穂後4週間の生息地(畦畔、雑草地、休耕田など)の除草は、カメムシ類を水田に追い込み、斑点米の発生を助長させるので避けましょう。
防除対策について
イネカメムシは、他の斑点米カメムシ類に比べて特にイネを好むため、除草管理だけでの防除は困難であり、薬剤による防除が必要になります。
また、若い穂を求めて水田から水田に移動するため、広域的に一斉に防除を実施することが効果的です。
薬剤による適期防除の実施(2回)
イネカメムシがイネを加害する出穂期~登熟初期に2回の薬剤防除を行いましょう。
なるべく広域で一斉に防除が実施できるように、地域内で調整を行いましょう。
1回目:出穂期~穂揃期(不稔の防止)
2回目:出穂期の8~14日後(斑点米の防止)
収穫後の耕うん
収穫後の再生株(ひこばえ)が秋の成虫・幼虫の餌資源となるため、収穫後は速やかに耕うんしましょう。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課 農政担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
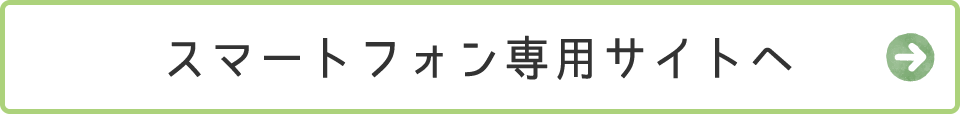


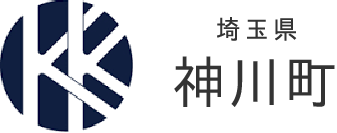
更新日:2025年05月01日